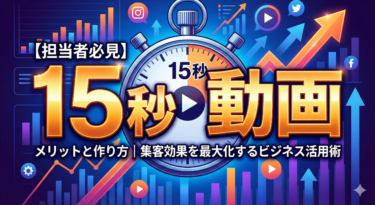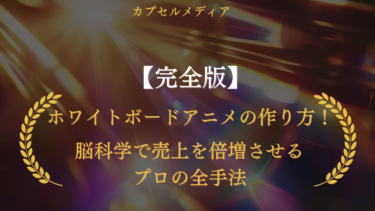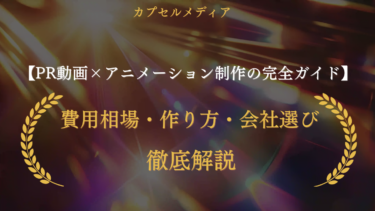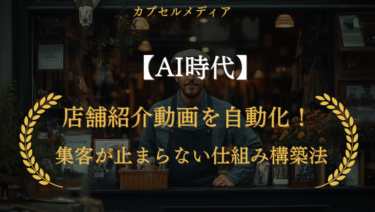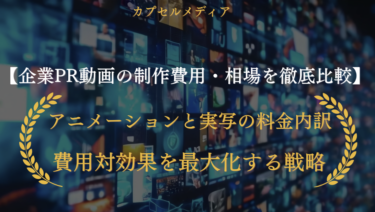オンデマンド配信とは?基本をやさしく解説
オンデマンド配信とは、あらかじめ収録した動画をインターネット上に公開し、視聴者が自分の好きなタイミングで見られる仕組みのことを指します。テレビのように「放送時間に合わせて視聴する」必要がなく、YouTubeの動画や動画配信サービスのように、視聴者の都合に合わせて再生できる点が大きな特徴です。
例えば、企業が商品説明の動画をオンデマンド配信として公開すれば、営業担当がいない時間でも、興味を持った人が自由に視聴できます。研修やセミナーの記録映像をオンデマンド化すれば、参加できなかった社員も後から確認できます。
このように「時間や場所に縛られない」利便性があるため、近年では企業のマーケティングや教育分野だけでなく、自治体や学校、個人クリエイターまで幅広く活用するようになっています。
ライブ配信とどう違うの?使い分けのポイント
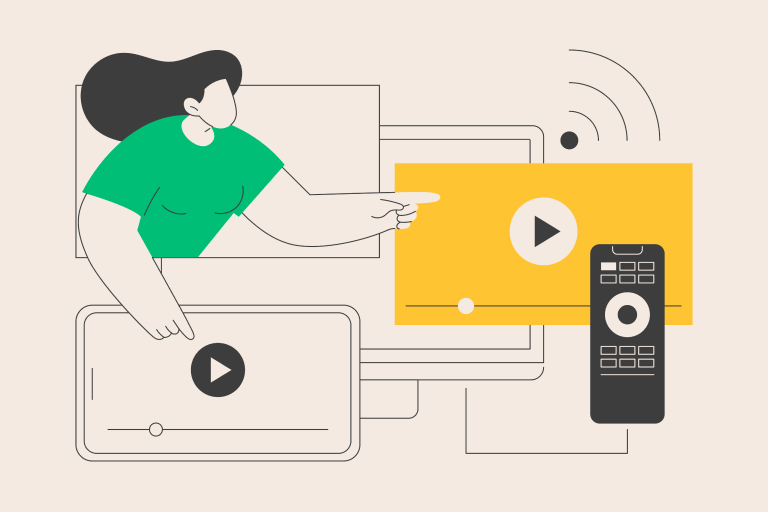
ライブ配信とオンデマンド配信には、それぞれ強みと弱みがあります。イメージをつかみやすいように表で比較してみましょう。
| ライブ配信 | オンデマンド配信 | |
|---|---|---|
| 視聴タイミング | 決まった日時にリアルタイムで視聴 | いつでも好きなタイミングで視聴可能 |
| 視聴者との交流 | コメントや質疑応答で双方向のやり取りがしやすい | 基本的に一方向。事前にアンケートやフォームを活用すると効果的 |
| コンテンツの特性 | 「臨場感」や「一体感」を共有できる | 繰り返し視聴できる「資産」として活用できる |
| 活用シーン | イベント、セミナー、記者発表など | 製品紹介、研修、教育、採用広報など |
| 準備・運営 | 配信当日の段取りが重要 | 撮影・編集など事前準備が必要 |
オンデマンド配信とよく比較されるのが「ライブ配信」です。名前の通り、ライブ配信はリアルタイムで映像を届ける方法で、オンラインイベントやウェビナーでよく使われています。一方のオンデマンド配信は、収録済みの動画を好きな時に再生できる仕組みです。
たとえば、商品発表会を考えてみましょう。リアルタイムの臨場感や視聴者との双方向のやりとりを重視するなら、ライブ配信が適しています。質問コーナーやチャットでの反応を通じて、その場の盛り上がりを演出できます。
一方で、後からじっくり情報を確認してもらいたい場合や、何度も繰り返し見て理解を深めてもらいたい場合はオンデマンド配信が便利です。時間に縛られず視聴できるため、忙しい人にも見てもらいやすく、動画の寿命を長くできる点が強みといえるでしょう。
どちらか一方だけを選ぶのではなく、目的に合わせて使い分けるのが理想です。ライブ配信でリアルタイムの熱量を伝えつつ、後日オンデマンドでアーカイブを公開すれば、多くの人に情報を届けられる効果的な組み合わせになります。
オンデマンド配信の活用シーンと種類
オンデマンド配信は「好きなときに視聴できる」という特性を持つため、企業や団体のさまざまな場面で活用されています。ここでは代表的なシーンを紹介します。
製品・サービス紹介
新しい製品やサービスを紹介する動画は、オンデマンド配信と相性が抜群です。
短い動画ならSNSやWebサイトに掲載し、いつでも閲覧できる形にすることで、営業担当者が直接説明できない場面でも役立ちます。特に複雑な仕組みを持つ製品は、動画で見せることで理解が早まり、商談のスピードアップにもつながります。
イベントやセミナーの記録
展示会やセミナーをオンデマンドで公開すれば、当日参加できなかった人にも情報を届けられます。
リアルタイム配信と比べて映像を丁寧に編集できるため、要点をまとめたダイジェスト動画や、講演ごとに分けて配信するといった工夫も可能です。これにより、イベントの効果を一過性で終わらせず、長期的な広報資産として活用できます。
社内研修・教育コンテンツ
社員研修や教育用コンテンツもオンデマンド配信の代表例です。
新入社員研修やマニュアル動画を一度制作しておけば、繰り返し利用できるためコスト削減にもなります。場所や時間に縛られず学習できるため、全国に拠点を持つ企業や在宅勤務の社員が多い組織にとっても効果的です。
採用や広報活動
採用活動では、会社説明会や社員インタビューをオンデマンド化することで、学生や求職者が自分のペースで視聴できます。
また、広報活動として社長メッセージやCSR活動の紹介を配信すれば、企業の姿勢や雰囲気をわかりやすく伝えることができます。限られた紙面や文章だけでは伝えきれない部分を、動画なら感覚的に届けられるのが魅力です。
導入するメリット(企業・団体・個人の視点から)
オンデマンド配信は、立場によって得られる利点が少しずつ異なります。ここでは、企業・団体・個人それぞれの視点から見たメリットを整理してみましょう。
企業にとってのメリット
企業にとって最大の魅力は「営業やマーケティング活動を拡張できる点」です。
製品説明や導入事例の動画をオンデマンド化しておけば、商談時だけでなく、見込み顧客が自分の都合の良い時間に視聴して理解を深められます。また、採用活動や社内研修でも活用できるため、人的リソースの削減や業務効率化につながるのも大きなメリットです。動画は一度作れば何度でも使えるため、長期的に見ればコスト面でも有利といえます。
団体・自治体にとってのメリット
自治体や団体にとっては「情報発信の継続性と広がり」が強みです。
地域イベントや観光PRの動画をオンデマンドで配信すれば、現地に足を運べない人にも魅力を伝えられます。さらに、自治体が実施する説明会や市民向けセミナーも録画して公開すれば、透明性の向上や地域住民との信頼関係構築につながります。多言語字幕を追加することで、海外への発信にも活用できる点も見逃せません。
個人にとってのメリット
個人にとっては「時間や場所に縛られない学習・発信」が最大の魅力です。
例えば、専門知識や趣味のノウハウを動画で配信すれば、自分の知識を共有できるだけでなく、副業や収益化のチャンスも広がります。また、オンライン講座や資格学習をオンデマンドで受講できれば、自分の生活スタイルに合わせて学べるため、効率的にスキルアップが可能です。移動時間を気にせず学習や情報収集ができるのは、現代のライフスタイルに合った利点といえるでしょう。
気をつけたいデメリットと対策
オンデマンド配信は便利で多くのメリットがありますが、導入前に注意しておきたい課題も存在します。ここではよく挙げられるデメリットと、その対策について解説します。
視聴を後回しにされやすい
ライブ配信と違い「好きなときに見られる」ことが特徴ですが、裏を返せば「今すぐ見なくてもいい」と思われがちです。その結果、再生されないまま忘れられてしまうケースもあります。
対策としては、配信後にメールやSNSでリマインドを行う、冒頭数十秒で引き込む工夫をする、といった視聴意欲を刺激する仕掛けが効果的です。限定公開期間を設定するのも有効な手段のひとつです。
コミュニケーション不足になりやすい
オンデマンド配信は一方向の情報発信になりがちで、視聴者とのリアルタイムなやり取りができません。これにより、双方向の関係構築が難しくなる場合があります。
この課題を補うには、コメント欄やアンケートフォームを設けて意見を集めたり、視聴者からの質問に答えるライブ配信を併用したりする方法が考えられます。オンデマンドとライブを組み合わせることで、双方の良さを活かせるでしょう。
配信準備に手間とコストがかかる
動画を撮影・編集し、配信環境を整えるには一定のコストと労力がかかります。特に初めて取り組む企業や団体にとっては、思った以上に負担が大きく感じられるかもしれません。
解決策としては、必要に応じて外部の制作会社やプラットフォームを活用することです。自社で全てを抱え込むのではなく、専門家の力を借りることで、効率的に質の高いコンテンツを用意できます。最初はシンプルな内容から始めて、徐々に拡張していくのも現実的な進め方です。
配信までの流れをステップごとに紹介

ステップ① 企画・構成を決める
まず大切なのは「誰に、どんな目的で伝えるのか」を明確にすることです。新商品を紹介するのか、社内向けの研修なのかで内容や伝え方は大きく変わります。テーマが決まったら、動画の長さや章立て、話す順序などを簡単にまとめておくと、その後の撮影や編集がスムーズに進みます。
ステップ② 動画を撮影・編集する
企画に沿って撮影を行います。特別な機材がなくても、最近はスマートフォンで十分きれいな映像を撮影できます。重要なのは「聞き取りやすい音声」と「見やすい構図」です。撮影後は不要な部分をカットしたり、文字や図を差し込んだりして、視聴者が理解しやすい形に仕上げます。
ステップ③ 配信サービスにアップロード
完成した動画は、YouTubeやVimeoなどの配信サービスにアップロードします。社外向けであれば公開範囲を「限定公開」に設定すれば、リンクを知っている人だけが視聴可能になります。社内向けの場合は、自社のイントラネットや専用サービスを使うケースもあります。
ステップ④ 視聴者に届ける・効果測定
配信しただけでは見てもらえません。メールや社内チャット、SNSなどを通じて告知し、視聴してほしい人にしっかり届けることが重要です。その後は再生回数や視聴時間、アンケート結果などを確認し、次回の動画改善につなげましょう。
オンデマンド配信ができるサービス7選
YouTube(無料で利用しやすい定番サービス)
誰でも気軽に始められるのがYouTubeです。無料で動画を公開でき、限定公開を使えば特定の人だけに視聴してもらうことも可能です。世界的に利用されているサービスなので、操作方法や活用事例も多く、初心者にとって安心感のある選択肢です。
Vimeo(高画質・広告なしでプロ向け)
広告が入らず、映像をきれいに見せたい場合にはVimeoが適しています。有料プランでは独自のプレイヤーを埋め込めたり、細かい視聴制限をかけたりできるので、ブランドイメージを重視する企業や、動画制作会社が採用するケースも増えています。
Zoom(録画データをオンデマンド化できる)
ウェビナーやオンライン会議でおなじみのZoomも、録画機能を使えばオンデマンド配信に活用できます。ライブ配信後にそのまま参加できなかった人へ録画を共有できるため、セミナーや説明会を繰り返し使いたい場合に便利です。
Microsoft Stream / SharePoint(社内利用に最適)
社内での情報共有を重視するなら、Microsoftのサービスが便利です。Office365との連携により、従業員のアカウントごとに視聴範囲を制御できます。社内研修やマニュアル動画など、外部に公開せず安全に扱いたい映像配信に向いています。
Brightcove(大規模配信に強い企業向けサービス)
Brightcoveは、世界中の大手企業や官公庁で導入されている動画配信プラットフォームです。安定した配信品質に加え、詳細な視聴ログの取得やマーケティングツールとの連携が可能で、顧客分析やリード獲得にも活用できます。イベントや製品紹介動画を資産として長期的に運用したい企業にとって、信頼性の高い選択肢です。
Kaltura(教育・社内研修に特化したプラットフォーム)
Kalturaは、大学や教育機関、企業の研修などに広く使われているサービスです。動画にクイズやアンケートを組み込むなど、インタラクティブな学習体験を提供できるのが特徴です。権限設定やセキュリティ面も充実しており、社外に出せないナレッジ共有やeラーニングをオンデマンド化したい場合に適しています。
Uscreen(課金型オンデマンド配信に強いサービス)
Uscreenは、動画コンテンツを販売したり、月額制のサブスク型サービスを構築したい企業やクリエイター向けのプラットフォームです。決済機能や会員管理システムが標準で備わっており、自社ブランドの動画配信サイトやアプリを作ることも可能です。オンラインスクールやD2C型の教育サービスを展開したい場合に有効なサービスです。
よくある質問と答え(Q&A)

Q1. オンデマンド配信とライブ配信、どちらを選べばいいですか?
A. リアルタイムでの双方向性を重視するならライブ配信、時間を問わず繰り返し視聴してもらいたいならオンデマンド配信が適しています。どちらか一方に決める必要はなく、イベントをライブで実施し、後からオンデマンドで公開する組み合わせも有効です。
Q2. 専門的な機材がないと始められませんか?
A. いいえ。スマートフォンやパソコンのカメラでも十分配信は可能です。もちろん画質や音質を上げたい場合は専用機材を検討するとよいですが、最初は身近な機材から始めても問題ありません。
Q3. 動画の長さはどれくらいが良いですか?
A. 目的によって変わりますが、研修やセミナーでは30分〜1時間程度、製品紹介や社外向けの発信なら5分〜15分程度が目安です。視聴者が集中できる時間を意識すると、最後まで見てもらいやすくなります。
Q4. 著作権には注意が必要ですか?
A. 音楽や画像、映像素材などは必ず権利関係を確認しましょう。特にYouTubeなど一般公開型のサービスでは、著作権侵害があると動画が削除されることもあります。商用利用を想定する場合は、フリー素材や自社制作の素材を使うのが安心です。
Q5. 社内だけで配信することは可能ですか?
A. 可能です。Microsoft Streamや専用プラットフォームを利用すれば、アクセス権限を設定して限られた人だけが視聴できる環境を整えられます。セキュリティを重視する企業や団体では、この仕組みがよく活用されています。
まとめ:オンデマンド配信を始める第一歩
オンデマンド配信は、視聴者が自分のタイミングで動画を楽しめる便利な仕組みです。企業にとってはサービス紹介やセミナーの継続的な活用に役立ち、団体や自治体では情報発信の幅を広げる手段となります。個人でも教育や趣味の発信など、さまざまなシーンで活用できます。
一方で、準備の手間や視聴者とのコミュニケーション不足といった課題もあります。しかし、企画の工夫や適切な配信サービスの選択によって、そのデメリットは十分に補えます。大切なのは「目的に合わせた動画を作り、きちんと届けること」。まずは小さな配信から始め、徐々にノウハウを蓄積していくのがおすすめです。
オンデマンド配信を始めるにあたって「動画制作のノウハウが足りない」「どう配信すればよいか分からない」と感じる方も多いかもしれません。カプセルメディアでは、企画から制作、配信までを一貫して支援し、目的に合った動画活用をお手伝いしています。安心して第一歩を踏み出せるよう、ぜひお気軽にご相談ください。