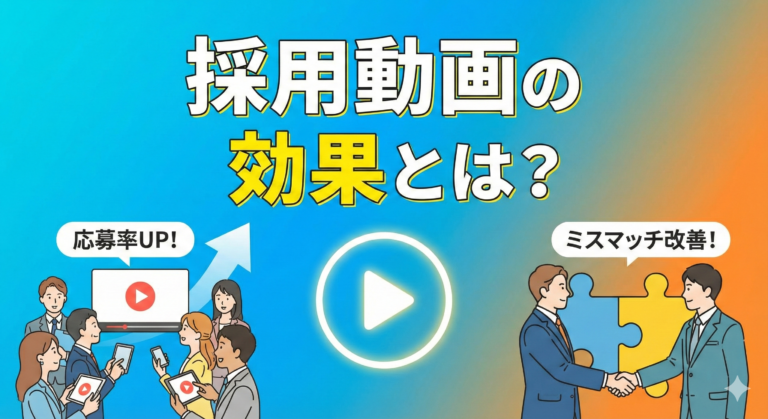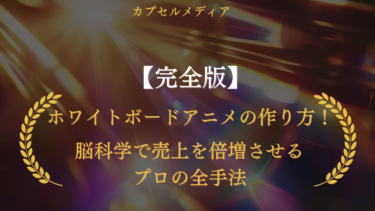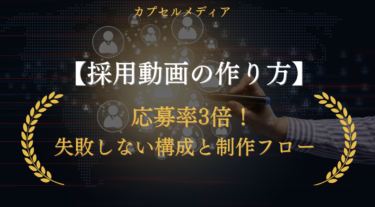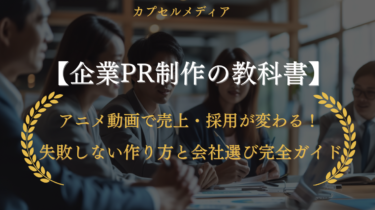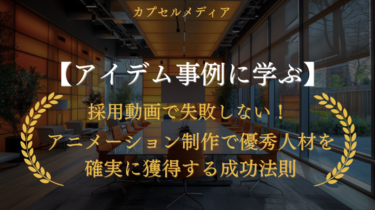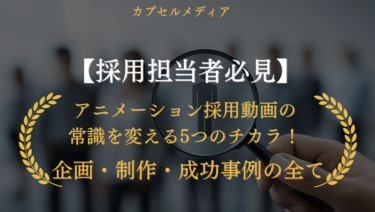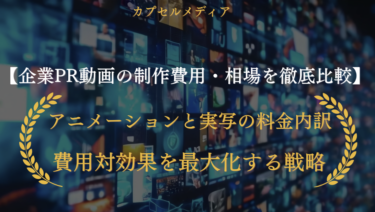はじめに:採用動画が注目される背景と今のトレンド
採用活動の情報戦が進む中で変わる伝え方
近年、採用の現場では「どんな会社かをどう伝えるか」がこれまで以上に重視されています。
求人票や説明会だけでは、会社の雰囲気や働く人の姿勢といった空気感までは伝えきれません。そこで注目を集めているのが、動画を使った採用ブランディングです。
採用動画の強みは、映像・音・テンポを通して、企業文化や価値観を感覚的に伝えられる点にあります。言葉では伝えにくい社内の空気や社員の表情を映すことで、応募者は「ここで働く自分」をリアルにイメージしやすくなるのです。
SNS・動画プラットフォームの普及が追い風に
さらに、YouTubeやTikTok、Instagramなど、動画が主流となったSNSの普及も大きな要因です。
就職活動中の学生や転職希望者の多くが、スマートフォンで企業情報をチェックする今、動画は最も自然な情報発信の形になりました。企業説明会の代わりにオンライン動画を活用したり、採用サイトにショートムービーを掲載したりといった事例も増えています。
また、動画は広告運用との相性も良く、採用広報を「マーケティング」として捉える企業も増えています。単なる求人ツールではなく、「ブランドメッセージを伝える映像コンテンツ」としての活用が、これからの採用戦略の中心になりつつあります。
採用動画がもたらす主な効果
認知度・ブランドイメージ向上
まず一番大きいのは「知ってもらう力」です。
採用動画を使うことで、まだ接点のない求職者にも企業の存在を印象的に伝えることができます。
特にYouTubeやSNSに掲載する場合、企業説明というより「ブランド紹介」に近い見せ方が効果的です。
たとえば、社員の姿勢やオフィスの雰囲気、社風が映像で自然に伝わると、それだけで「この会社、雰囲気いいな」と感じてもらえる。
これは文章や写真だけでは難しい部分です。
ブランドの第一印象づくりとして、動画の役割は年々大きくなっています。
応募率アップ・応募者の質改善
動画をきっかけに「ここで働きたい」と思う人が増えるのも、よくある効果です。
実際、採用サイトに動画を加えるだけで応募数が増えたケースは多くあります。
特に動画では、社員のリアルな声や職場の空気感を伝えられるため、「自分に合いそう」と感じた人だけが応募しやすくなります。
結果として、単に応募数が増えるだけでなく、ミスマッチの少ない質の高い応募につながるのです。
ミスマッチ削減・リテンション向上
動画を導入してから「入社後のギャップが減った」と話す企業も増えています。
実際に働く現場や先輩社員のリアルな一日を映すことで、求職者が事前に具体的な働き方をイメージできるからです。
面接時の「思っていた雰囲気と違う」といったズレが減ることで、早期離職の防止にもつながります。
採用動画は採用広報であると同時に、定着率アップのためのツールでもあるんです。
コスト・工数の削減
一度制作した動画は、説明会・採用サイト・SNSなど複数の場面で再利用できます。
担当者が毎回説明する手間を減らせるため、長期的に見るとコスト削減効果が高いのも特徴です。
また、オンライン説明会やインターン募集ページなど、動画一本で複数の採用施策をカバーできるのもポイント。
採用チームのリソースが限られている企業にとっては、非常に効率的な手段といえます。
社内文化浸透・社員ロイヤルティの強化
意外と見落とされがちですが、採用動画は社内向けの効果もあります。
制作の過程で社員がインタビューに参加したり、普段の仕事風景を撮影したりすることで、改めて「自社の良さ」を再認識するきっかけになるんです。
完成した動画を社内で共有すれば、社員のモチベーションアップや一体感の醸成にもつながります。
つまり採用動画は、社外への発信ツールであると同時に、社内文化を育てるツールとしても活用できるというわけです。
効果を裏付けるデータと事例紹介
採用動画は感覚的に良さそうという段階を超えて、実際に数値として効果が裏付けられ始めているツールです。
ここでは、学生・求職者を対象にした調査データと、実際に改善が報告されている事例を紹介します。
学生・求職者アンケート調査の数値例
採用動画が「求職者の気持ちにどれほど影響を与えているか」を調べた調査はいくつか存在します。
たとえば、就職・転職経験者を対象に行われたアンケートでは、
「採用動画を見たことがある企業があるか」という質問に対し、73.3%が「1回以上ある」と回答。
さらに「採用動画は企業選びの際にあった方が良いと思うか?」という問いでは、約75%が「そう思う」と答えています。
この結果から、採用動画はすでに「あると嬉しい」ではなく、あって当然の情報ツールになりつつあることが分かります。
また、別の調査では「採用動画を視聴した後に志望度が上がったか?」という質問に対し、
「大きく上がった」45.9%、「上がった」39.9%と回答。
つまり、視聴者の8割以上が志望度の上昇を感じているという結果です。
この数字は、採用動画が単なるPRコンテンツではなく、求職者の意思決定に直接影響を与えるツールであることを示しています。
成功企業の具体的な改善数値(応募数・離脱率・早期退職率など)
採用動画の導入によって実際にどんな変化が起きているのか。
公開情報はまだ多くありませんが、いくつか参考になるデータがあります。
前述の調査によると、採用動画を視聴した応募者の約80%が志望度を上げたと回答しており、これは応募意欲の向上につながる傾向を示しています。
さらに、「採用動画を見たことがある」と回答した人が7割を超える一方で、「採用動画がある企業の方が印象が良い」と答えた人も約75%にのぼっています。
これは、採用動画を持たない企業は、他社比較で印象面で不利になる可能性があることを意味します。
加えて、求職者の間では「複数企業を比較する際、動画の有無が印象を左右する」という回答も見られ、
動画は応募動機の形成だけでなく、企業選びの判断基準にもなっていることが分かります。
ただし、離職率や内定承諾率といった導入前後比較の具体的な数値を公開している企業はまだ少なく、
実際の効果検証は、自社内でKPI(応募率・内定率・定着率)をもとにモニタリングするのが現実的です。
出典:
効果を高めるための動画設計のポイント

ターゲットとフェーズ(認知~興味~行動)に応じた構成
採用動画を作るときに最初に考えるべきなのは、「誰に」「どの段階で」見てもらう動画なのか、という点です。
動画を一本にまとめようとすると、つい全部入りにしてしまいがちですが、目的が違えば伝え方も変わります。
たとえば、
- 認知フェーズでは「どんな会社?」を印象的に伝えるブランディング動画。
- 興味フェーズでは「どんな人が働いているの?」にフォーカスした社員インタビュー動画。
- 行動フェーズでは「どう応募すればいい?」を明確に示す採用案内や募集要項の動画。
このようにフェーズごとに役割を分けて動画を設計すると、視聴者の離脱も減り、必要な情報がスムーズに届くようになります。
ストーリー設計・演出・リアリティの取り入れ方
次に大切なのが「ストーリー」です。
採用動画と聞くと、「社員インタビューを並べればいい」と思われがちですが、それだけでは印象に残りません。
視聴者が最後まで見たいと思う流れを意識することが重要です。
たとえば、
- 社員の1日に密着するドキュメンタリー風
- 入社前後の変化を追うストーリー型
- ナレーションと映像を組み合わせたメッセージ型
など、構成の方向性を最初に決めておくと、撮影から編集まで一貫性が生まれます。
また、採用動画で特に大切なのがリアリティです。
最近の求職者は映像の演出に敏感で、「作られた感じ」が強すぎると逆に冷めてしまうことがあります。
社員の自然な表情や、普段のやり取りが少し映るだけでも、企業の空気感はしっかり伝わります。
動画の長さ・フォーマット・媒体の選び方(説明会/Web/SNS)
効果的な採用動画は、使われる場面に合わせた長さと形式になっています。
たとえば:
- 会社説明会用:3〜5分でストーリー重視。会場の雰囲気に合わせて音声も明瞭に。
- Webサイト掲載用:1〜3分で要点を凝縮。トップページに置くなら導入15秒が勝負。
- SNS配信用(Instagram・TikTok・YouTube Shorts):15〜60秒で印象的な一言を入れる構成が効果的。
採用動画は「長ければ伝わる」わけではなく、目的に合った長さでまとまっているかが効果の差を生むポイントです。
どの媒体に、どの瞬間に、どんな求職者が触れるのか。
そのイメージを持ちながら設計すると、動画はより強いメッセージを持つようになります。
採用動画を運用する方法と効果測定の仕組み
公開チャネルと配信タイミング
採用動画は「作ったら終わり」ではなく、どこで、いつ、誰に届けるかによって成果が大きく変わります。
同じ動画でも、使う場所が違えば見られ方や反応はまったく別物になります。
たとえば、
- 説明会で上映すれば、会場の雰囲気づくりや参加者の集中力に影響します。
- 採用サイトに掲載すると、企業理解を深める補足として機能します。
- SNSで配信すれば、まだ検討前の層にも“軽い入口”として届きます。
また、配信タイミングもポイントです。
説明会前に送る事前視聴用として活用したり、内定後のフォローとして“会社の雰囲気を思い出してもらうための動画”として使う企業もあります。
採用動画は単発のプロモーションではなく、一年を通して候補者との接点をつくるコミュニケーションツールとして扱う方が、結果的に効果が長続きします。
KPI設定と効果の定期レビュー
採用動画の効果を測るには、目的に合ったKPI(指標)を設定することが欠かせません。
動画の使い方によって、見るべき数字はまったく変わります。
たとえば:
- 認知を広げたい
→ 再生回数、SNSの反応、視聴完了率 - 応募につなげたい
→ 動画から採用ページへの遷移数、応募フォームまでの到達率 - 説明会の理解度を上げたい
→ アンケートでの印象や理解の深さ
最初から数字を細かく追う必要はありませんが、「何のための動画か」だけは先に決めておくことが重要です。
動画を公開した後は、社内で月1〜四半期ごとのタイミングで数字を見返し、「どこを直せばもっと見てもらえるか?」「採用ページの動線は使いやすいか?」などを軽くレビューしていくと、運用が安定していきます。
A/Bテスト・改善サイクルの考え方
採用動画は、一度作って終わりだと当たり外れが出やすいものです。
そのため、小さなA/Bテストを繰り返して改善するという考え方が向いています。
たとえば:
- 冒頭のカットを変えて、どちらが離脱されにくいかを比較する
- サムネイルやタイトルを変えてクリック率を検証する
- ナレーションの有無で視聴の伸び方を比べてみる
こうした細かな検証を積み重ねると、何が響くかが感覚ではなく、数字として見えてきます。
採用動画は、広告動画ほどシビアな調整が必要ではありませんが、ちょっとした改善を続けるだけで成果がじわじわ上がるツールでもあります。
- 反応を見る
- 必要な部分だけ手直しする
- また配信して反応を見る
このサイクルをゆっくり回すことで、動画は“作って終わりのもの”ではなく、
長く使える採用資産になっていきます。
効果を損なわない演出・よくある失敗例

過度な演出で「らしくない」印象になるリスク
採用動画の制作で最も多い失敗のひとつが、かっこよくしすぎることです。
映像のクオリティを上げようと、派手なBGMやテンポの速いカットを多用すると、一見華やかに見えますが、実際の会社の雰囲気とかけ離れてしまうケースが少なくありません。
特に中小企業や地域密着型の会社では、「動画の印象=会社の印象」になりやすく、ギャップが生まれると逆効果です。
例えば、実際はアットホームな職場なのに、動画ではスタイリッシュなオフィス風に仕上げてしまうと、応募後の面談であれ、思ってた雰囲気と違う…となることもあります。
求職者は、企業が思っている以上にリアルな情報を求めています。
トレンド感よりも、「自社らしさ」や「日常の温度感」を伝えるほうが、結果的に好印象につながることが多いです。
演出を加えるときは、目的を明確にして、「誰に」「どんな印象を残したいのか」を常に意識しておくと失敗しません。
動画と他採用ツール(求人票・説明会等)との整合性
もうひとつ見落とされがちなポイントが、動画と他の採用ツールとの整合性です。
たとえば、求人票や企業サイトでは「挑戦できる社風」を打ち出しているのに、動画では和気あいあいとした雰囲気を強調してしまう。
このようなトーンのズレは、求職者に「本当の姿が見えない」という不信感を与えてしまいます。
採用活動全体を一つのストーリーとして捉え、求人票 → 動画 → 面接 → 内定が自然に繋がる流れを作ることが重要です。
動画単体の完成度よりも、他ツールとの情報の一貫性を優先したほうが、結果的に効果が高まります。
採用動画は、会社の「入口」として見られることが多いです。
そのため、他ツールとの整合性を意識しながら、会社のストーリー全体の一部として設計するのが理想です。
派手な演出やトーンのズレは、一瞬で動画の信頼性を損ないます。
大切なのは、「見る人の期待と、実際の会社像がズレないこと」。
採用動画の目的は「かっこよく見せる」ではなく、「リアルな魅力を伝える」ことを忘れないようにしましょう。
採用動画にかかる費用・制作体制との関係
採用動画の制作費は、内容や目的によって大きく変わります。
一般的には30万〜150万円前後が相場と言われますが、最近はスマホアプリや社内ツールを活用して数万円で制作するケースも増えています。
ただし、「費用=効果」ではないという点を理解しておくことが大切です。
ここでは、予算のかけ方や制作体制によってどう成果が変わるのかを整理してみましょう。
費用をかけた場合と予算を抑えた場合の「効果の違い」
まず、しっかり費用をかけた採用動画の強みは、クオリティと印象のコントロールがしやすいことです。
プロの撮影・編集チームが入ることで、ライティングや音声、テンポ感まで計算された映像に仕上がり、視聴者の記憶に残る動画を作ることができます。
特に、ブランディングや認知目的の採用動画では、一定以上の品質が成果を左右します。
一方で、予算を抑えた社内制作やテンプレート動画でも、社風やリアルな雰囲気を伝えるには十分な場合があります。
特に中小企業では、社員が自分の言葉で語るシーンに信頼感が生まれ、結果的に応募の質が高まることも少なくありません。
つまり、費用をかけるかどうかは「見せたい印象」と「採用フェーズ」によって判断するのがポイントです。
たとえば、認知拡大にはプロ制作、社内紹介には自社制作など、目的に応じて使い分けるのが理想的です。
自社内制作か外注か、どちらが効果を出しやすいかの比較
採用動画の制作体制は、大きく「自社制作」と「外注制作」に分かれます。
それぞれの特徴と向いているケースを整理すると、次のようになります。
| 制作方法 | メリット | デメリット | 向いているケース |
| 自社制作(インハウス) | コストを抑えられる/スピーディーに更新可能/社内の空気感をそのまま出せる | 映像クオリティが不安定/構成や演出のノウハウが必要 | 現場密着型、社員紹介動画、SNS用の短尺動画など |
| 外注制作(プロダクション) | 高品質で印象に残る映像が作れる/構成・演出・撮影すべて任せられる | 費用が高め/修正に時間がかかる場合がある | コーポレートブランディング、説明会用ムービー、採用サイトTOP動画など |
結論としては、「すべてをどちらかに任せる」のではなく、ハイブリッド型が最も効率的です。
メインの採用ムービーを外注で制作し、日常の更新コンテンツ(社員の声やイベントの様子)を社内で撮影・編集する。
こうすることで、ブランド力と発信スピードの両立が可能になります。
実際に大手企業でも、採用動画の年間スケジュールを「プロ制作+内製更新」で運用しているケースが増えています。
動画制作のコストは単発ではなく、年間を通してどう活かすかという運用視点で考えると、より効果的に使えます。
動画の制作費は、単なる支出ではなく、投資です。
採用動画の目的と運用期間を明確にしたうえで、どこにリソースをかけるべきかを整理すれば、費用対効果は大きく変わります。
よくある質問(FAQ)
採用動画をやれば必ず応募数が増える?
正直に言うと、「動画を作っただけで応募数が劇的に増える」というケースはあまりありません。
採用動画はあくまで採用戦略全体の一部であり、他の要素(求人内容・募集条件・掲載面・時期)と組み合わせて効果を発揮します。
ただし、動画を導入した企業の多くは、応募者の「質」が向上しています。
具体的には、「うちの社風に合いそうな人が増えた」「面接辞退が減った」といった声が多いです。
これは、動画を通じて職場の雰囲気や働く人のリアルな姿が伝わり、応募前にギャップを埋められるからです。
つまり、採用動画は応募数よりもマッチング率の改善に強いツールです。
目的を「応募を増やす」ではなく、「ミスマッチを減らす」と設定することで、より効果的に活用できます。
効果が出るまでにどれくらい時間がかかるの?
これは配信方法や業界によって差がありますが、一般的には3〜6か月程度で変化が見え始めます。
公開直後は再生数が伸びなくても、採用サイトや求人票、SNSなどで繰り返し露出するうちに、徐々に認知と応募行動に繋がっていきます。
特に採用動画は「短期的な広告」ではなく、資産型のコンテンツです。
動画を1本作ることで、説明会・HP・SNS・求人媒体など複数の場面で再利用でき、半年〜1年をかけて成果を積み上げていくのが基本です。
また、効果を早く出したい場合は、配信チャネルの設計が鍵になります。
YouTube広告やInstagramリール、採用サイトのトップ埋め込みなど、視聴導線を最初から設計しておくと、初動から反応が取りやすくなります。
一度作った動画はどれくらいの期間有効?更新は必要?
採用動画の賞味期限は、だいたい1年〜2年が目安です。
映像そのものが古くなるというより、社内の人・制度・オフィス環境などが変化するため、内容が現状とズレてしまうのが主な理由です。
動画の更新タイミングを見極めるポイントは以下の3つです。
- 出演社員が退職した・部署が変わった
- 採用ターゲットや職種が変わった
- 会社の制度やオフィスが刷新された
このような変化があった場合は、全面リニューアルよりも一部差し替え・再編集で対応するのがおすすめです。
撮影素材をうまく残しておけば、ナレーションやテロップだけの修正で再利用でき、コストも抑えられます。
採用動画は「作って終わり」ではなく、「更新しながら育てる」コンテンツです。
定期的に見直すことで、常に今の会社の姿を伝えられるようになります。
まとめ:採用動画の効果を最大化するためのアクションリスト

採用動画は、単に「かっこいい映像を作る」ことが目的ではなく、採用活動全体を底上げするためのツールです。
とはいえ、作って終わりにしてしまうと、せっかくの動画も十分に力を発揮できません。
ここでは、動画の効果を最大化するために押さえておきたいポイントを整理しておきましょう。
1. 目的とターゲットを明確にする
まず一番大切なのは、「誰に」「何を伝えたいか」を決めることです。
新卒向けなのか、中途向けなのか。職種は営業職か、技術職か。
ターゲットが違えば、伝えるメッセージも映像のトーンも変わります。
採用動画を作る前に、「この動画を見た人にどう感じてほしいのか?」を社内で共有しておくと、ブレのない構成にできます。
2. 動画を単発ではなく運用資産として活用する
採用動画は一度作ったら終わりではなく、運用して初めて効果が出るコンテンツです。
説明会、採用サイト、SNS、求人ページなど、複数の場所で繰り返し活用しましょう。
YouTubeやInstagramに切り抜きを投稿するだけでも、想像以上に反応が変わります。
制作後の配信設計をきちんと行い、再生データを定期的にチェックして改善を続けることで、成果はどんどん伸びていきます。
3. 「自社らしさ」を軸に演出を考える
採用動画で最も大切なのは、リアリティと一貫性です。
派手さよりも、自社の人らしさや日常の空気感を大切にしたほうが、求職者の共感を得やすくなります。
撮影では、社員の自然な表情や、現場での何気ない会話などを積極的に取り入れてみてください。
「飾らない姿」が、最も強いブランディングになることもあります。
4. データで効果を確認し、定期的にブラッシュアップする
動画を公開したら、再生数や視聴維持率、応募数の変化などを追いかけてみましょう。
数字をもとに効果を把握することで、次に改善すべきポイントが見えてきます。
特におすすめなのは、半年ごとの軽い見直しです。
ナレーションを差し替えたり、新入社員のコメントを追加したりするだけでも、鮮度を保ちながらコストを抑えられます。
5. 社内外のパートナーと協力して作る
動画制作は、採用担当だけで完結するものではありません。
現場の社員や広報チーム、時には外部の制作会社とも連携しながら進めることで、より多角的でリアルな内容に仕上がります。
伝える側の熱量が映像に乗ると、視聴者にもその思いが伝わります。
ぜひチーム全体で、動画づくりを会社のプロジェクトとして取り組んでみてください。
採用動画の制作は「会社の魅力を再発見するプロセス」
採用動画を作る過程は、単なる映像制作ではなく、自社の魅力を言語化・可視化する作業でもあります。
社員の声を拾い、日常の風景を映し出すことで、「自分たちの強み」や「働く意義」を再確認できるきっかけにもなります。
カプセルメディアのご紹介
私たちカプセルメディアは、企業の採用やブランディングに特化した映像制作を行っています。
「伝わる構成」と「人の温度感」を大切にしながら、リアルな魅力を映像化することを得意としています。
採用動画を初めて検討される企業様でも、目的設計から構成・撮影・運用まで一貫してサポート可能です。
もし「うちの会社らしさをどう表現すればいいか分からない」という場合は、まずはお気軽にご相談ください。
カプセルメディアの制作実績
【動画実績】採用エージェント様のアニメーション
企業様版求人サイトアニメーション動画実績
韓国エンジニア紹介会社のアニメーション動画制作