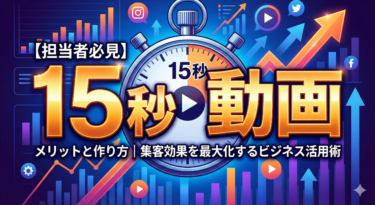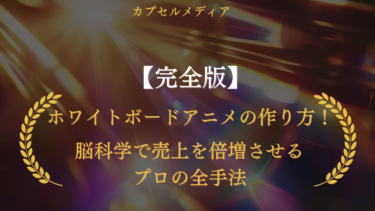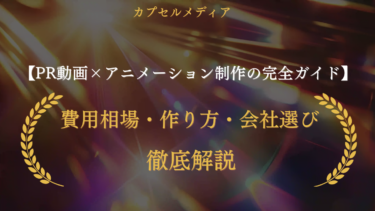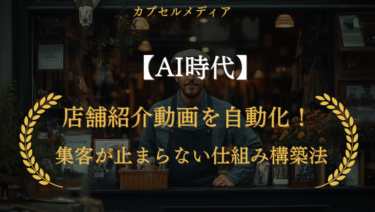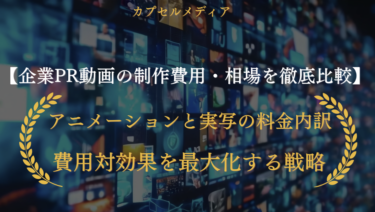プレゼン動画とは?基本の定義と活用シーン
プレゼン動画とは何か?
「プレゼン動画」とは、口頭での説明やスライド資料を映像としてまとめたもので、視聴者に情報をわかりやすく伝えるための手段として活用されます。
一般的なプレゼンテーションと異なり、時間や場所を問わずに再生できるのが大きな特徴です。
映像であることで視覚と聴覚の両方に訴えかけられるため、資料だけでは伝わりにくい熱意やニュアンスまで届けることが可能になります。
また、プレゼンターの話し方や表情、アニメーションによる補足表現など、視聴者の理解や記憶に残りやすい設計ができる点も、プレゼン動画ならではの強みです。
なぜ今、プレゼン動画が注目されているのか?
ビジネスの現場では、オンライン化・非対面化の流れが急速に進んでいます。対面での営業や説明が難しくなった今、動画による情報共有のニーズが高まり、プレゼン動画の活用が広がっています。
たとえば、次のようなケースで導入されることが増えています:
- 営業活動の代替手段として(サービスや製品の紹介動画)
- 新卒・中途採用の会社説明資料として
- 投資家向けのIR資料を動画化
- セミナーやウェビナーの事前資料として
- 社内研修や教育用コンテンツ
このように、プレゼン動画は「一度作れば何度でも活用できる」資産となり、コスト削減や業務効率化にもつながります。
プレゼン動画の特徴まとめ
| 特徴 | 内容 |
| 時間・場所に左右されない | いつでもどこでも視聴可能 |
| 情報の伝達力が高い | 映像+音声で理解しやすい |
| 資産として活用できる | 社内外で繰り返し使用できる |
| 制作の自由度が高い | ナレーション、スライド、アニメーションを組み合わせられる |
プレゼン動画の制作事例
【動画実績】PDF資料をアニメーション化
棒科学機器メーカーの会社紹介アニメーション動画
【動画実績】不動産事業進出コンサルティング
プレゼン動画を導入する3つのメリット
ビジネスの現場で「プレゼン動画」を導入する企業が増えています。その背景には、従来のプレゼン手法では得られなかった伝達力・効率性・コスト効果が関係しています。ここでは、プレゼン動画を導入することで得られる主なメリットを3つに絞ってご紹介します。
時間・場所を問わず伝達可能
従来のプレゼンテーションは、基本的に「その場に集まって話を聞く」ことが前提でした。しかし、動画を使えばその制約がなくなります。
例えば営業資料を動画にしておけば、担当者が不在でも商談相手に視聴してもらえます。海外のパートナーや、時差のある取引先に向けて説明を行いたい場合にも非常に有効です。
また、プレゼン動画は一度作れば何度でも使用できるため、情報の一貫性を保ちながら、必要な人に必要なタイミングで届けることが可能です。
効率的な情報伝達・理解促進
文字や静止画だけでは伝わりづらい内容も、動画なら動きや音声を使ってわかりやすく表現できます。話し手のトーンや表情、図解アニメーションなどを交えることで、視聴者の理解を深めることができます。
また、内容を「導入 → 結論 → 理由 → まとめ」といった論理的な構成で展開すれば、聞き手は自然と内容を吸収できます。難しい専門用語や複雑な仕組みも、動画であれば視覚的に噛み砕いて伝えることができるのです。
特に、初対面の相手や新規顧客に向けたプレゼンでは、情報を早く・正確に伝える工夫が大切。動画はその点でも大きな力を発揮します。
プレゼンター負担の軽減とコスト削減
プレゼン動画は、プレゼンターの負担軽減にもつながります。何度も同じ内容を説明する必要がなくなり、担当者の工数を大幅に削減することができます。
また、社内説明会や採用説明会、営業研修などで何度も同じ資料を使う場面では、毎回プレゼンターが登壇するよりも、動画を流す方が圧倒的に効率的です。
さらに、出張費や移動時間、準備の手間といった隠れたコストも削減できます。1本の動画が、複数の拠点や担当者をカバーする「営業マン代わり」になることも少なくありません。
このように、プレゼン動画は「ただ便利なだけ」のツールではなく、ビジネス全体の効率と成果を底上げしてくれる戦略的なコンテンツです。
次章では、実際にプレゼン動画を作るときの基本的な流れについて、わかりやすくご紹介します。
失敗しないプレゼン動画の制作ステップ

プレゼン動画は「撮れば終わり」というわけではありません。伝わる動画をつくるには、事前の設計や段取りがとても重要です。ここでは、企画から完成までの基本的な制作ステップを整理してご紹介します。
1. 目的とターゲットの整理(企画)
まず最初にすべきことは、「誰に」「何を」伝えるかを明確にすることです。
- この動画は営業用なのか、それとも採用活動用なのか?
- 視聴者は業界知識のある人か、それとも初見の人か?
ここが曖昧なまま進めてしまうと、どんなに編集で見栄えを整えても、伝えたいことがぼやけてしまいます。動画の方向性を決める設計図を作るつもりで、この段階にしっかり時間をかけることが重要です。
2. シナリオと構成の設計
目的とターゲットが定まったら、それに基づいてシナリオ(台本)と構成案をつくります。
プレゼン動画では、情報を順序立てて伝えることが大切です。一般的には、
- 導入(興味を引く)
- 本題(サービスや製品の説明)
- 根拠やデータの提示
- まとめ・行動喚起
という流れが多く使われます。
また、ここで画面上に表示するスライドやアニメーション、ナレーションの内容も決めていきます。後の撮影・編集をスムーズに進めるためにも、構成段階で細かく詰めておくことがポイントです。
3. 撮影または素材の準備
構成が決まったら、いよいよ素材の準備に入ります。撮影が必要な場合は、プレゼンターの立ち位置やカメラアングル、照明なども丁寧に調整します。
自社で撮影する場合は、音声のクリアさや背景のノイズにも注意を。プロに依頼する場合でも、目的や構成の共有がきちんとできていれば、スムーズな進行が可能です。
なお、アニメーションやスライド中心の動画にする場合は、撮影なしでも十分なクオリティに仕上げられるケースもあります。
4. 編集・仕上げ
撮影素材やスライドが揃ったら、編集作業に入ります。ここでは、ナレーションやBGMの挿入、テロップの追加、色味の調整など、細部の「見せ方」を整えていきます。
編集では、視聴者の集中力を保つ工夫が欠かせません。不要な間をカットしたり、重要な箇所にエフェクトを入れたりと、テンポよく伝えるための調整が求められます。
また、スマホ視聴が多い場合は縦型動画にしたり、音声オフでも内容が理解できるよう字幕を入れるなど、視聴環境を意識した対応も大切です。
5. 試写・フィードバック・微調整
初稿の動画が完成したら、関係者でチェックを行います。構成通りに進んでいるか、音声が聞き取りにくくないか、意図がきちんと伝わっているかなどを確認します。
必要に応じてナレーションを録り直したり、テロップを修正したりして、最終版に仕上げていきます。視点を変えて見直すことで、細かな改善点が見つかることもあります。
効果的なプレゼン動画にする5つのポイント
プレゼン動画は「ただ伝える」だけでなく、「いかに相手の記憶に残し、理解を促すか」がカギになります。せっかく作るなら、しっかり効果のあるコンテンツにしたいところ。
ここでは、プレゼン動画をより印象的で伝わるものにするための、5つの工夫ポイントをご紹介します。
1. 冒頭のインパクト(オープニング動画)
動画の冒頭は、いわばつかみの場面。ここで視聴者の注意を引けなければ、最後まで見てもらうことは難しくなります。
・課題提起(「こんなお悩みありませんか?」)
・印象的な一言
・アニメーションやビジュアルの演出
こうした仕掛けを使って、最初の数秒で「この動画は自分に関係がありそうだ」と思ってもらうことが大切です。特にSNSやWeb広告などでは、最初の5秒が勝負とも言われています。
2. 複数動画を隙間に挟む設計
1本に情報を詰め込みすぎてしまうと、視聴者は疲れてしまい内容も頭に入りません。そこで効果的なのが、複数の短い動画に分割する設計です。
例えば、
- オープニング
- 製品・サービスの特徴
- 導入事例
- よくある質問
といったように、それぞれのテーマごとに独立した動画にすることで、視聴者は自分に必要な部分だけを選んで見られるようになります。これにより、視聴のストレスを軽減し、離脱を防ぐことができます。
3. 各動画は60~90秒以内に
プレゼン動画の1本あたりの長さは、60秒~90秒程度が理想的とされています。それ以上長くなると、集中力が続かず、途中で離脱されるリスクが高まります。
伝えたいことが多い場合は、前述のように複数の動画に分割することが鉄則です。短い時間でも伝わるよう、内容を絞り込み、構成を練ることが成功のポイントです。
4. 「導入→結論→理由→結論」の構造で構成
プレゼン動画は、論理的で理解しやすい構成にすることが欠かせません。特におすすめなのが、
導入 → 結論 → 理由・根拠 → 再度結論
という構成。
これは、視聴者が「何の話なのか」「なぜそう言えるのか」をすぐに把握できるため、内容が頭に残りやすくなります。
たとえば製品紹介であれば、
- 導入:課題を提示
- 結論:自社の製品がそれを解決する
- 理由:その理由や実績、特徴を説明
- 再結論:もう一度、魅力を明確に伝える
という流れにすることで、伝えたいポイントがブレずにしっかり届きます。
5. アニメーションやデモをシンプルに活用
動画の強みは、視覚的に情報を伝えられることです。特に複雑な情報や仕組みを説明するときは、アニメーションやデモ映像が有効です。
ただし、やりすぎには注意。情報が多すぎたり、動きが派手すぎたりすると逆効果です。説明の補助として、シンプルな図解やアニメーションを活用することで、理解を助けながらテンポよく進められます。
SEO効果と押さえておくべき配信戦略
プレゼン動画は「伝えるためのツール」であると同時に、Web集客やSEO(検索エンジン最適化)においても強力な武器となります。
正しい形で活用すれば、検索順位の向上やコンバージョン率の改善につながるケースも少なくありません。ここでは、動画が持つSEO効果と、それを活かすための配信戦略について解説します。
Webサイトへの埋め込みで滞在時間を向上
まず、動画を自社サイトに埋め込むことで期待できるのが、「ページ滞在時間の向上」です。
検索エンジンは、ユーザーがそのページでどれだけ時間を過ごしたかを評価指標のひとつとしています。テキストだけのページよりも、動画があることで滞在時間は伸びやすくなり、それがSEO評価の向上に直結します。
特にサービス紹介や採用ページなど、ユーザーの理解を深めたいページでは、プレゼン動画の埋め込みが効果的です。
YouTubeとの併用で検索露出を強化
動画をYouTubeにアップロードすることで、Google検索の動画タブやYouTube検索経由の流入も狙えます。
また、YouTubeに掲載した動画は、Googleがクロール・インデックスしやすいため、検索結果にも表示されやすくなるというメリットがあります。
動画のタイトルや説明文、タグに狙いたいキーワードを自然に含めておくことで、検索エンジンにも内容を伝えやすくなり、SEO面での相乗効果が期待できます。
YouTubeにアップした動画は、ブログやLP(ランディングページ)などにも埋め込めるため、運用の幅も広がります。
動画による被リンク獲得の可能性
質の高いプレゼン動画は、他のWebサイトやブログ、SNSなどで紹介されることもあります。これはいわゆる被リンクの獲得につながり、SEOでは非常に重要な要素とされています。
特に、サービスや業界に関する有益な情報を整理したプレゼン動画は、同業他社や業界メディアからの紹介対象にもなりやすく、自然な形で外部リンクが増える要因になります。
動画コンテンツは「共有されやすい」という特性もあるため、SNSでの拡散を視野に入れておくとさらに効果的です。
SNSやメール配信との連動も重要
WebサイトやYouTubeだけでなく、SNSやメールマガジンといったチャネルでの再利用も、配信戦略としては非常に有効です。
例えば:
- LinkedInやX(旧Twitter)で短く編集したバージョンを投稿
- メールで既存顧客へ動画付きで情報提供
- 展示会後のフォローとして動画リンクを送付
など、動画は1回作って終わりではなく、複数の場面で再利用しやすいコンテンツです。視聴者の接触回数を増やすことで、理解促進や興味関心の維持にもつながります。
プレゼン動画は「魅せるだけ」のツールではなく、集客やSEO戦略の中心にもなりうる重要な要素です。動画をどこで・どう活用するかまで設計することで、制作の投資対効果も大きく変わってきます。
次の章では、外注する場合のポイントや、動画制作会社の選び方についてご紹介します。
事例紹介:実際に成果を出したプレゼン動画

プレゼン動画は、業種や目的に応じてさまざまな活用が可能です。ここでは、実際に成果を出している具体的な活用事例をいくつかご紹介します。
「どんな使い方があるのか」「本当に効果が出るのか」といった疑問をお持ちの方の参考になれば幸いです。
採用説明動画:短時間で企業の魅力を伝える
ある製造業の中堅企業では、合同説明会でのプレゼン時間が限られていたため、企業紹介や社員の声をまとめた採用用プレゼン動画を導入。
結果として、動画を見た学生からの「会社の雰囲気がよく伝わった」「働く姿がイメージできた」といった声が多数寄せられ、説明会後の応募率が前年比の約1.4倍に増加しました。
動画にすることで、「社風」「仕事のリアル」「職場の様子」といったテキストでは伝わりにくい部分をしっかり届けることができた好例です。
営業用動画:商談前に興味を引き、理解を深める
BtoBサービスを提供するIT企業では、営業担当が訪問前にメールでプレゼン動画を送るスタイルを導入。
サービスの概要や導入メリットを短くまとめた動画により、初回の打ち合わせでの理解度が大きく向上し、「資料よりも分かりやすかった」という反応も多く得られました。
結果として、商談成立率が以前より20%以上アップし、営業担当者の説明時間も短縮され、効率と成約率の両面で成果が見られました。
社内研修用動画:教育の効率化と理解度アップ
ある物流会社では、社員研修を動画化し、現場での教育に活用。これまで現地でのOJTに依存していた内容を、「導入→実例→注意点」といった構成で動画にまとめました。
その結果、担当者の教育負担が軽減されただけでなく、社員側も自分のペースで繰り返し学習できる環境が整い、研修の満足度が大幅に向上しました。定着率や作業ミスの減少といった効果も見られ、社内からの評価も高い取り組みとなっています。
このように、プレゼン動画は採用・営業・教育など、社内外を問わずさまざまなシーンで活用可能です。
単なる説明にとどまらず、「伝えたいことが確実に届き、行動を生む」ための手段として、動画がいかに強力かがわかります。
次章では、動画制作を依頼する際に押さえておくべきポイントをご紹介します。
よくある質問(FAQ)とその回答
プレゼン動画の制作を検討されるお客様から、よくいただくご質問をまとめました。初めて制作を依頼される方も、ぜひご参考になさってください。
プレゼン動画の最適な長さはどのくらいですか?
一般的には「1本あたり60〜90秒」が目安です。
人の集中力は意外と短く、特に初めて見る動画の場合は、2分を超えると視聴完了率が落ちていく傾向があります。
ただし、用途によって適切な長さは異なります。採用説明や研修動画など、じっくり見てもらう前提の動画であれば3〜5分程度になることもあります。
大切なのは「情報量」ではなく「伝わりやすさ」です。
ナレーションは入れるべきですか?
基本的には入れることをおすすめします。
ナレーションがあると、視覚と聴覚の両方から情報を伝えられるため、理解度や記憶に残る効果が高まります。
ただし、展示会など音が出せない環境での使用を想定している場合は、字幕ベースでの構成にするなど、使用シーンに合わせた工夫が必要です。
スライドや資料は何枚用意すれば良いですか?
スライドの枚数に厳密な決まりはありませんが、「1分あたり3〜5枚」が目安です。
テンポよく内容が進むと、視聴者の興味を引き続けやすくなります。
ただし、1枚に情報を詰め込みすぎると逆に伝わりづらくなるため、1枚1メッセージを意識した構成が効果的です。
音質やBGMにはどれくらいこだわるべきですか?
実は、動画の印象を大きく左右するのが音声品質です。
ナレーションの声がこもっていたり、BGMが大きすぎたりすると、それだけで視聴者の集中力が途切れてしまいます。
プロのナレーターによる収録、適切な音量調整、場面に合ったBGMの選定など、映像と同じくらい音にも気を配ることが、完成度を高めるポイントです。
構成はどうやって決めればいいですか?
構成は動画の目的に合わせて決めるのが基本です。
よく使われるのは「導入 → 結論 → 理由 → 結論」という構成型で、特にビジネス動画では効果的とされています。
・導入:興味を引くオープニング
・結論:一番伝えたいメッセージ
・理由:その裏づけやメリット
・結論:改めて伝えたいことを強調
この流れを意識することで、視聴者が迷わず内容を理解しやすくなります。
これらのポイントを押さえることで、プレゼン動画のクオリティと効果は大きく変わってきます。
「どう進めていいかわからない」といった場合も、企画段階からご相談いただければ、最適な内容をご提案いたします。お気軽にご相談ください。
まとめ:プレゼン動画は伝える力を最大化するビジネスツール
プレゼン動画は、ただ情報を伝える手段ではなく、「印象に残し、行動を促す」強力なコミュニケーションツールです。
採用、営業、社内教育、IR、サービス紹介など、あらゆるビジネスシーンで活用できる柔軟性と効果があります。
- 時間や場所を問わず届けられる利便性
- 視覚と聴覚を活かした情報伝達力
- 社内の業務効率化にもつながる汎用性
一方で、構成や尺、音声のバランスなど、成果に直結する設計の工夫が求められる分野でもあります。
目的に合った動画を、確かな戦略のもとで制作することが、成功の鍵です。
カプセルメディアについて
私たちカプセルメディアは、企業様の「伝えたい」を最も効果的に届ける動画制作会社です。
プレゼン動画をはじめ、採用・営業・商品紹介・会社案内・SNS広告・YouTube運用など、幅広いジャンルの映像制作に対応。
ヒアリングから企画・撮影・編集・納品・配信サポートまでをワンストップで対応し、ビジネス成果に直結する動画をご提供します。
特に当社では、構成力と目的設計に重きを置いており、
「何を誰に、どう届けるか?」という視点から、御社の強みや魅力を最大限に引き出す表現をご提案しています。
プレゼン動画の制作を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。