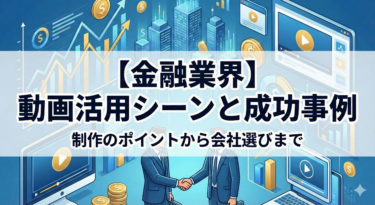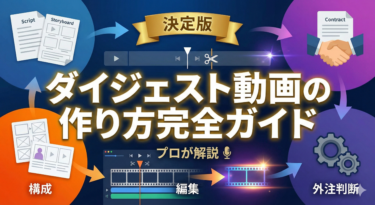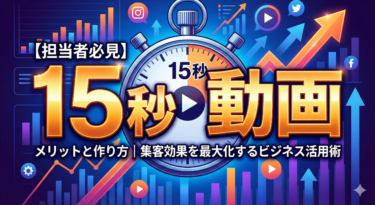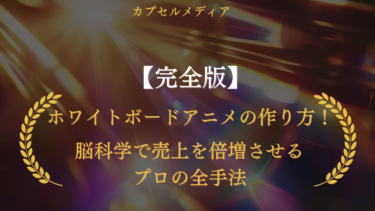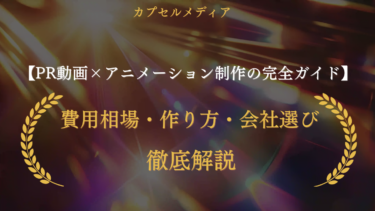面白い動画とは?
面白い動画が注目を集める理由
SNSやYouTubeを眺めていると、思わず笑ってしまう「面白い動画」が目につきます。人が笑う瞬間というのは強い感情の動きであり、記憶に残りやすいのが特徴です。さらに「自分だけが知っている面白さを誰かに共有したい」という心理も働きます。その結果、自然にシェアや拡散が広がり、多くの人の目に触れるようになります。
つまり、面白い動画は「楽しさ」と「共有したい気持ち」の両方を刺激することで、注目を集めやすいのです。
面白い動画とアイデアの関係
面白い動画には必ず工夫されたアイデアが存在します。漫然と撮った映像では笑いは生まれません。ちょっとした仕掛けや視点の切り替え、日常を違う角度から見せる工夫が「面白さ」につながります。
たとえば、同じ商品紹介でも「真面目に説明する」よりも「予想外の演出」を加えた方が印象に残ります。ここで大切なのは、大がかりな企画だけがアイデアではないということ。小さな工夫やユニークな切り口でも、十分に面白い動画は成立します。
面白さが生まれる要素(ギャップ・意外性・共感)
面白い動画が成り立つ背景には、いくつかの共通する要素があります。
- ギャップ:普段は真面目な人が突然ユーモアを見せるなど、期待とのズレが笑いを生みます。
- 意外性:予想外の展開やオチは、視聴者を驚かせ、同時に笑いを誘います。
- 共感:日常の「あるある」や身近な体験を映した動画は、多くの人に刺さりやすく、「自分も同じだ」と共感を呼びます。
これらの要素を上手に組み合わせることで、誰もが「つい最後まで見てしまう」面白い動画が完成します。
面白い動画の成功事例〜企業・商品PR編〜
株式会社石井工機
株式会社石井工機が公開している企業紹介動画は、一見するとシンプルな映像構成です。逆光を背に社員が堂々と歩いてくるシーンや、カメラ目線で腕を組み直立するカットなど、映画のワンシーンを思わせる演出が随所に盛り込まれています。まるで大企業のブランディング映像か、スポーツブランドのCMを彷彿とさせるような力強い表現です。
しかし舞台となっているのは、実は「町工場」。最先端のテクノロジー企業でもなく、世界的ブランドでもない。そのギャップが生み出すユーモラスさこそが、この動画の最大の魅力と言えます。本来であれば真面目に技術や製品を解説するはずの紹介映像に、映画的な照明とカメラワークを持ち込み、社員一人ひとりをヒーローのように映し出す。その過剰なカッコよさが逆に笑みを誘い、視聴者の記憶に強烈に残ります。
ビジネスの観点から考えると、このような表現は単なる遊び心では終わりません。町工場という業態は「堅実」「実直」「地味」といったイメージを持たれがちですが、その枠を超えて発信することで、採用活動や取引先への印象を大きく変える可能性を秘めています。特に若手人材にとっては、「町工場=古い」という固定観念を覆し、むしろ面白そうな会社と映る効果が期待できます。
つまり石井工機の動画は、映像演出としてはユーモラスでありながら、ブランディング戦略としては非常に理にかなったものです。逆光や腕組みといったベタな演出をあえて真剣にやりきることで、会社の姿勢そのものを鮮やかに伝えていると言えるでしょう。
本田技研工業
本田技研工業が公開したTVCM「MOVE」篇は、世界的ブランドのスケール感を活かした斬新な映像表現が光る作品です。映像は深夜の高速道路を走るバイクシーンから始まりますが、不思議なことに画面に映るのはライダーだけ。車体そのものは消えており、人が宙に浮かぶように運転している姿が次々と描かれます。山道を走るライダー、船を操縦する人物、F1レーサー、そして昭和期の開発者の喜びの瞬間まで、どの場面でも「乗り物」そのものは見えず、人間の姿だけが強調されているのです。
このユニークな演出は、単に奇抜さを狙ったものではありません。「モビリティは人を主役にするもの」というブランドの哲学を象徴的に映し出しています。最後に「人を動かす力を夢と呼びたい」というキャッチコピーとともに、Hondaが生み出してきたバイク、車、飛行機といったプロダクトが一斉に登場。これまでの歴史と未来への挑戦が一瞬で視覚化され、深い余韻を残します。
また、この映像を際立たせているのが、菅野よう子による楽曲「Blue feat. Maya」。静けさと力強さを併せ持つ旋律が、映像全体に普遍的な広がりを与えています。Hondaという大企業だからこそ成立する発想であり、製品そのものを映さずに「ブランドの精神」を描き切る手法は、グローバル企業の広告戦略の中でも稀有な成功例といえるでしょう。
株式会社三越伊勢丹ホールディングス
株式会社三越伊勢丹ホールディングスが2014年に公開した「ISETAN-TAN-TAN」プロモーション動画は、百貨店ならではの遊び心と団結力を表現したユニークな作品です。
楽曲は矢野顕子氏によるオリジナルソング「ISETAN-TAN-TAN」。彼女の伊勢丹への深い愛情から生まれたこの曲に合わせて、日本国内の各店舗や海外拠点で働く従業員約500名が踊る様子を収録しています。ダンスの振り付けはPerfumeを手掛けるMIKIKO氏が担当。初心者から上級者まで楽しめるよう3段階に分けた構成と、臨場感あるカメラワークによって、映像全体が伊勢丹の店内を巡るような体験を生み出しています。
この映像の魅力は、従業員一人ひとりの真剣さと楽しげな笑顔にあります。普段は接客を担うスタッフが、仲間とともに踊る姿を通して「伊勢丹は楽しい場所」という企業の姿勢を伝えているのです。さらに、ダンスというコミュニケーション表現を用いたことで、社内の一体感を高めるだけでなく、視聴者にもポジティブなエネルギーを届けることに成功しました。
公開後、YouTubeでの再生数は伸び続け、社内外の話題を呼びました。従業員の笑顔と音楽、そして洗練された演出が融合したこの映像は、百貨店のブランド価値を体現すると同時に、グローバル発信を可能にした新しい広告表現の好例といえるでしょう。
株式会社キングジム 「HITOTOKI CLOCK」
キングジムの文房具ブランド「HITOTOKI」が2017年に公開した「HITOTOKI CLOCK」は、日常の一分一秒を愛おしく過ごすというブランドの哲学を映像で表現した、ユニークな作品です。
この映像の最大の特徴は、24時間をかけてワンカット撮影された「手づくりの時計」という構成。1,440分=1,440のシーンに合わせて3,000点以上の小道具を入れ替え、背景の色まで1分ごとに変化させることで、時間の流れを丁寧に描き出しています。アクセスした時刻に応じて再生される「リアルタイム版動画」も公開され、視聴者が自分の「いま」を体感できる仕組みになっています。
本作の魅力は、効率やスピードを追い求める現代社会に対して、「一手間かけることの豊かさ」を伝えている点にあります。スタッフは24時間を通じて手作業で撮影を続け、細部にまで工夫を凝らしました。そのアナログな制作過程自体が、ブランドのメッセージ「時間をデザインして過ごす」を象徴しています。
「HITOTOKI CLOCK」は、デジタル時代における世界一アナログなデジタルコンテンツとも言える存在であり、ブランデッドコンテンツの新しい可能性を切り開いた事例といえるでしょう。
日清食品 カップヌードル「7 SAMURAI」
日清食品が2016年に公開したカップヌードルのグローバルCM「7 SAMURAI」篇は、2014年から話題を集めてきたSAMURAIシリーズの続編として制作されました。過去作の総再生回数は3,000万回に迫り、今回も公開直後から世界各国で注目を集めました。
映像の舞台は、ブラジルの街や海辺、雪山といった多彩なロケーション。そこに現れるのは、甲冑を身にまとった7人のサムライたち。彼らは重装備のまま、サーフィン、スケートボード、BMX、スキー、スラックライン、ポゴスティック、フリースタイルフットボールといったエクストリームスポーツに挑みます。しかも演じるのは、それぞれの分野で世界的に活躍するトップアスリート。圧倒的なパフォーマンスは周囲の人々を惹きつけ、やがて観衆が熱狂の渦に包まれていきます。
この大胆な演出を支えているのは、キャッチコピー「CRAZY MAKES the FUTURE.」。 世界を動かすのは、常識を超える熱量と情熱だ。同じバカなら、世界を沸かせるバカになれというメッセージが込められています。甲冑とストリートカルチャーを融合させたユニークな世界観は、グローバルブランドならではの挑戦であり、従来の食品CMの枠を大きく超えた表現です。
SAMURAIシリーズは、カップヌードルが長年掲げてきた「ユニークで挑戦的な広告戦略」の象徴ともいえる存在。伝統と革新を同時に描くこの映像は、単なる商品訴求を超え、世界中の若者に「情熱が未来を変える」というインパクトを残しました。
一般財団法人関西電気保安協会 「関西電気保安協会ゲーム」
2025年に公開された『関西電気保安協会ゲーム』は、海外ドラマさながらの緊迫感と、関西ならではのユーモアを融合させたユニークな啓発映像です。
作品の最大の特徴は、「関西人しかいないデスゲーム」という舞台設定。主人公が見知らぬ場所で目を覚まし、マスコットキャラクター「ホアンくん」がゲームマスターとして試練を課すというストーリーが展開されます。生き残りをかけた緊迫したシーンの合間に、コミカルな演出や会話が差し込まれ、電気保安という堅いテーマを親しみやすく伝えています。
本作の狙いは、日常生活に不可欠でありながら若年層には馴染みの薄い「電気保安」を、エンターテインメントを通じて身近に感じてもらうことにあります。
シリアスと笑いのバランス、そしてマスコットキャラクターを絡めた演出は、硬直化しがちな公共的メッセージに遊び心を取り戻した事例ともいえるでしょう。
『関西電気保安協会ゲーム』は、地域に根ざす公益団体が動画表現の可能性を拡張した作品であり、エンターテインメントを活用した社会啓発の好例として記憶されるはずです。
面白い動画の成功事例〜リクルート・採用動画編〜
株式会社トクミツ建築企画
株式会社トクミツ建築企画が制作した採用動画は、一般的な企業紹介やリクルート映像とは一線を画すユニークなアプローチをとっています。動画の設定は、就職活動中の学生が「面接官」となり、企業側が必死に自社の魅力を伝えるという逆転の構図。社長や社員が一生懸命に会社の強みを説明する姿は、シリアスでありながらも演技の誇張や映像演出によってユーモラスに描かれています。
特に印象的なのは、学生があくまで淡々と質問を投げかける一方で、企業側が必死に答えを返すシーン。形式的でよくある質問内容が題材となっているため、視聴者は面白さを感じながらも、自然に「この会社はどんな事業をしているのか」「どのような強みがあるのか」を理解できるようになっています。結果として、映像全体がドラマ仕立てのテンポを持ちながらも、採用広報としての役割をしっかり果たしている点が大きな特徴です。
また、こうした遊び心ある映像手法は、若い世代に対して強い印象を与える効果があります。従来の真面目すぎる採用動画では伝えにくい「柔軟さ」や「挑戦する姿勢」を、演出そのものが象徴しているため、会社のカルチャーを映像を通してダイレクトに訴求できていると言えるでしょう。
株式会社トクミツ建築企画は「図面を描く」という専門性の高い業務を担う企業ですが、この採用動画によって、業務内容だけでなく社風や魅力を視覚的かつ感覚的に伝えることに成功しています。従来型の説明では届きにくい層にリーチし、ブランディングにもつながる優れた事例といえるでしょう。
株式会社イメージランド
Imagelandが手掛けた採用動画は、レストランを舞台にしたユーモラスかつ業界風刺的な演出が特徴的です。冒頭はごく普通のカップルの食事シーンから始まりますが、男性が「ステーキの写真を撮るから食べるのを待って」と彼女に伝える場面から物語が展開。スマートフォンで撮影するはずが、なかなか納得のいく写真が撮れず、やがて照明を当てるために彼女に協力を求め、隣の客まで巻き込むなど、次第に「撮影現場化」していくユーモアが際立ちます。
特に印象的なのは、映像制作のプロセスを巧みにパロディ化している点です。いつの間にか照明スタッフ、ディレクター、音声担当が現れ、さらに別室にはクライアントが控えるという、本格的な映像制作現場さながらのシチュエーションに発展。専門用語が飛び交い、職人同士のこだわりや調整が繰り広げられる様子は、業界を知る人には「あるある」として共感を呼び、一般の視聴者には映像制作の奥深さと熱量をユーモラスに伝えています。
やっと「OK」が出るものの、新たな料理が運ばれてきて再び撮影が始まる、そんな展開の末に「来たれ新人」というキャッチコピーが表示され、採用動画としてのメッセージが鮮明に浮かび上がります。映像業界のリアルを笑いに昇華しつつ、同時に「情熱を持って取り組む仲間を求めている」という会社の姿勢を強く印象づける構成です。
彼女が終始呆れ顔であるというコントラストも絶妙で、「業界人にとっては当たり前だが、外から見ると滑稽に映る」というギャップを際立たせています。結果として、採用動画でありながらブランディング要素も強く、若い視聴者層に「この会社は面白い」と印象づける優れた事例だといえるでしょう。
マルコメ株式会社
味噌を中心とした食品メーカー、マルコメが公開した新卒採用向け動画は、研究開発職で内定を得た社員が営業職に挑戦する姿を追った、ドキュメンタリー仕立ての作品です。
動画は「なぜ営業を選んだのか」「営業の魅力とはなにか」を軸に展開。糀甘酒を発酵甘味料として全国に広めようとする取り組みをストーリーの核に据え、食品業界ならではのチャレンジの現場を描いています。
尺は約7分とやや長めですが、ナレーションやテロップを巧みに活用し、テレビ番組のようなテンポで進行するため、最後まで視聴者を引き込みます。社員自身が調理に挑戦する場面など、意外性ある要素も織り込み、自由な社風と営業職のやりがいを自然に訴求している点が特徴です。
採用動画としては「情報番組やバラエティの編集スタイル」を導入することで、説明的になりがちな採用広報にエンターテインメント性を加えています。これにより、若い世代にとって親しみやすく、同時に企業の挑戦的な姿勢を体現する映像となっています。
面白い動画の成功事例〜観光・地域PR編〜
宮崎県小林市 移住促進PRムービー「ンダモシタン小林」
宮崎県小林市が公開した移住促進PRムービー「ンダモシタン小林」は、美しい映像とユーモアを巧みに組み合わせた作品です。物語はフランス人青年が小林での暮らしを語るところから始まります。小さな林なのに「小林」と名乗る町、蛇口をひねれば天然水が出るのにペットボトルが売られている不思議さ、満天の星空があるのにプラネタリウムもある日常。そんな矛盾のようで豊かな環境をユーモラスに指摘しながら、小林の魅力を伝えていきます。
映像は映画のように美しく、落ち着いたピアノBGMが重なることで、フランス映画を思わせる上質な雰囲気を演出しています。観る人は自然と「小林って面白い場所だな」と感じ、移住先としての豊かさを直感的に理解できるのです。
そしてラストには衝撃のオチ。これまで流暢なフランス語と思われていた青年の言葉は、実は地元の方言「西諸弁」だったと明かされます。この意外性が強烈な印象を残し、笑いとともに小林市の文化の深さを刻みつけるのです。
この動画の魅力は、観光や移住を単純に美化するのではなく、「不思議さ」や「ユーモア」を前面に出している点にあります。他にはない切り口で街の個性を表現し、地域ブランディングの新しい手法を示した成功例といえるでしょう。
宮崎県小林市 PRムービー 山奥篇
宮崎県小林市が公開した市民応援PRムービー「山奥」篇は、わずか30秒という短い尺ながらも、強烈なインパクトを残す映像です。物語は山で遭難した登山者が、突如現れた神様に助けを求めるところから始まります。期待に胸を膨らませる登山者に対して、神様が説明を始めるものの、その言葉はすべて「西諸弁」。独特の方言で語られる帰り道の説明は全く理解できず、視聴者も登山者と同じく「???」状態に。さらに追い打ちをかけるように、伝わらないことを悟った神様が「What?」とだけ口にして、笑顔で消えてしまうというシュールな展開で幕を閉じます。
一見すると単なるコントのようですが、この動画の魅力は「地域アイデンティティ」をユーモアに昇華している点にあります。小林市の誇りである西諸弁は、外から来た人にとっては理解が難しいかもしれませんが、逆にそれを前面に押し出すことで「地域色の濃さ」や「地元のユニークさ」を強烈に印象づけています。短い映像ながらも、笑いを通じて「この町には他にない文化がある」というメッセージをしっかりと伝えているのです。
また、プロモーション戦略としても秀逸です。近年の地域PR動画は美しい風景や温かい人柄を前面に出すものが多い中、この映像はあえて伝わらない方言を武器にしています。結果としてSNSやYouTubeで拡散されやすく、短時間で話題性を生む構造になっているのです。地域ブランディングにおいて「弱みを強みに変える」好例であり、地方自治体の映像活用に新しい視点を示した取り組みといえるでしょう。
維新dancin’鹿児島市 スペシャルムービー
鹿児島市が公開したスペシャルムービー「維新dancin’鹿児島市」は、観光PRをユーモアと迫力で包み込んだ独自の映像作品です。登場するのは、ネットでも話題を集めている鹿児島実業高校男子新体操部。彼らは浴衣姿に西郷隆盛風のつけ眉毛を装い、観光地を背景に創作ダンスを披露します。ユニークな見た目に思わず笑ってしまいますが、その身体表現は一流。全国的にも知られる彼らの実力が、映像に確かな説得力を与えています。
楽曲のサビでは「維新dancin’鹿児島市」というフレーズが繰り返され、耳に残るリズムとともに観光スポットの魅力が次々と映し出されます。桜島や天文館、歴史ロードや磯海水浴場といった名所が、ダンスの熱気と重なることで鮮やかに印象づけられるのです。単なる観光紹介にとどまらず、「楽しさ」「勢い」「エネルギー」を感じさせる仕上がりとなっています。
この動画の特徴は、鹿児島の歴史や文化を真面目に遊ぶ姿勢で表現している点です。西郷隆盛や維新のイメージを大胆に取り込みながらも、現代的なエンターテインメントへと昇華。観る人を笑顔にしながら街の魅力を伝えるという、PR映像の新しい可能性を示した成功例といえるでしょう。
面白い動画を作るメリット

SNSで拡散されやすい効果
SNSを開くと、タイムラインには「笑える動画」や「ちょっとしたユーモアのある映像」が必ず流れてきます。なぜなら、人は面白いものを見つけると「誰かに見せたい」と思うからです。これはマーケティング的に言えば自然な拡散につながります。
広告を打たなくても、ユーザー自身が友人やフォロワーにシェアしてくれる。その結果、少ない労力で多くの人にリーチできるのが、面白い動画の大きな魅力です。
ブランドや商品認知を高める方法
真面目な商品紹介だけでは、なかなか人の心に残りません。しかし、ちょっと笑えるシーンやユニークな演出を加えるだけで、「あの面白い動画の会社」と覚えてもらえるようになります。
たとえば、採用動画にユーモアを交えると、「この会社は雰囲気が良さそう」と感じてもらえることもあります。面白さは単なる娯楽ではなく、ブランドや商品の印象をプラスに変える力を持っています。
広告費削減や集客につながる可能性
通常、企業が自社を広めるには広告費をかける必要があります。しかし、面白い動画は自然に再生数やシェアを伸ばすため、結果的に広告費を抑えることができます。
さらに、話題性のある動画は「見に来る」きっかけを作ります。イベントや店舗に人を呼びたいときにも効果的です。言い換えると、面白い動画は「宣伝しなくてもお客さんが集まる仕組み」をつくるツールになり得るのです。
面白い動画アイデアの発想法
日常の出来事から面白さを見つける
特別なセットや大がかりな演出がなくても、日常の中には面白い瞬間がたくさんあります。
たとえば、オフィスでの「あるある」や、家庭でのちょっとした失敗談。普段は見過ごしてしまう出来事も、切り取り方次第で立派な動画のアイデアになります。
視聴者は「自分もそういう経験ある!」と共感しやすく、共感が笑いにつながるのです。
トレンドや話題を取り入れるアイデア
SNSやニュースで話題になっているネタを取り入れるのも効果的です。
流行の音楽や人気のハッシュタグを組み合わせると、それだけで再生される確率が上がります。たとえば、TikTokのダンスや流行りのフレーズを活用すれば、ユーザーが「最新のノリ」に触れている感覚を楽しめます。
トレンドに便乗することは、面白い動画のアイデアを効率よく形にする方法のひとつです。
他業界・異分野から学ぶユニークな発想
面白い動画を考えるとき、自分の業界だけを見ているとアイデアが固まりがちです。そんなときは、まったく違う分野からヒントをもらうと新鮮な発想が生まれます。
たとえば、スポーツの演出を商品紹介に応用したり、料理番組風に会社紹介をしてみたり。異分野のスタイルを取り入れると、視聴者に「こんな見せ方があるんだ」と思わせることができます。
シンプルだけど刺さる面白い動画の作り方
必ずしも凝った映像や複雑な編集が必要なわけではありません。短くても、シンプルな仕掛けで十分に笑いを取れることがあります。
ポイントは「誰でもすぐ理解できる内容」にすること。たとえば、表情の変化や一言のセリフだけでも、視聴者をクスッとさせられることがあります。
難しく考えすぎず、シンプルさの中にユーモアを込めることが、面白い動画づくりの基本です。
面白い動画を作るときの注意点
炎上しないためのアイデアの線引き
面白い動画を作るときに一番注意したいのは「笑い」と「不快」の境界線です。見ている人を笑わせるつもりが、特定の人や属性を傷つけてしまうと炎上につながります。
たとえば、容姿や国籍をネタにしたユーモアは誤解を招きやすく、避けるべきです。代わりに「日常のちょっとしたあるある」や「予想外の展開」で笑いを取るほうが安全で、多くの人に受け入れられます。アイデアを出すときは、「もし自分が見たらどう感じるか」を一度立ち止まって考えることが大切です。
著作権や音楽利用のルール
もうひとつ注意が必要なのが著作権です。人気の楽曲や映画のワンシーンをそのまま使うと、権利侵害になる可能性があります。SNSにアップした動画が削除されるだけでなく、法的なリスクにつながることもあるので要注意です。
安心して使うには、フリー素材の音楽や、自社で契約している音源を活用するのがベストです。最近は商用利用できるBGMや効果音も多く公開されているので、上手に取り入れれば「オリジナル感」を出しながら安全に制作できます。
ブランドイメージとユーモアのバランス
面白さを追求するあまり、ブランドイメージを壊してしまっては本末転倒です。たとえば、高級感を売りにしている企業があまりにふざけた動画を出すと、逆に信頼を失う可能性があります。
ユーモアを取り入れるときは、自社の雰囲気や伝えたい価値観と合っているかを確認しましょう。「親しみやすさを伝える」「社員の人柄を見せる」といった目的に沿ったユーモアなら、ブランドを損なうどころかむしろ強化につながります。
面白い動画をビジネスに活かす方法

広告やSNSで活用する方法
面白い動画は単に楽しませるだけでなく、広告やSNS運用にも大きな力を発揮します。
広告として配信すれば、一般的なプロモーション動画よりも高い視聴完了率を狙えます。さらにSNSに投稿すれば、自然な形でフォロワーがシェアしてくれるため、広告費以上の拡散効果が期待できます。
ポイントは「プラットフォームに合った見せ方」を意識すること。Instagramでは短くテンポ良く、YouTubeでは少しストーリー性を持たせるなど、場所に合わせた工夫が必要です。
面白い動画の効果を測定する指標
動画を作った後は、効果を測定することも欠かせません。
代表的な指標は以下の通りです。
- 再生数:どれだけ多くの人が見たか
- エンゲージメント(いいね・コメント・シェア):視聴者の反応がどれだけあったか
- 視聴維持率:最後まで見てもらえたか
- クリック率やコンバージョン率:動画から実際の行動につながったか
単純な「再生数」だけでなく、どの指標がビジネスの成果につながるのかを意識すると、次の動画制作に生かしやすくなります。
継続的に発信するためのアイデアストック法
一度だけ面白い動画を作って終わり、では効果は限定的です。継続的に発信するためには、アイデアをストックする習慣が必要です。
おすすめは、日常の中で「ちょっと笑えた出来事」をメモしておくこと。社員やチームで共有すれば、思わぬネタが動画の種になることもあります。
また、定期的にトレンドをチェックして「今なら使えるアイデア」を蓄積しておくと、制作がスムーズになります。こうした工夫が、安定して面白い動画を生み出す土台になります。
まとめ
SNSやYouTubeで拡散される面白い動画には、いくつか共通した工夫があります。テンポの良さや意外性、そして視聴者の感情を揺さぶる要素がうまく組み合わさることで、ただ笑えるだけでなく「思わず人にシェアしたくなる」コンテンツになるのです。アイデアひとつで日常の出来事が大きな反響を生むのも、動画ならではの魅力といえるでしょう。
そして、そうした動画をしっかりと形にするには制作の技術や経験が欠かせません。動画制作会社カプセルメディア では、エンタメ性のあるSNS動画から企業のPR映像まで、幅広いジャンルに対応。視聴者を惹きつけるストーリー作りや映像演出を得意とし、「ただ流すだけの映像」ではなく「心に残る動画」を提供しています。
これから面白い動画を作って発信したい方にとっても、映像制作のプロと一緒に取り組むことで、アイデアがさらに磨かれ、より多くの人に届くコンテンツへと成長していくはずです。